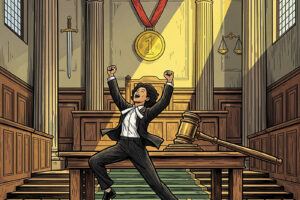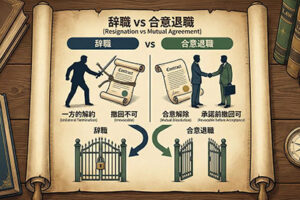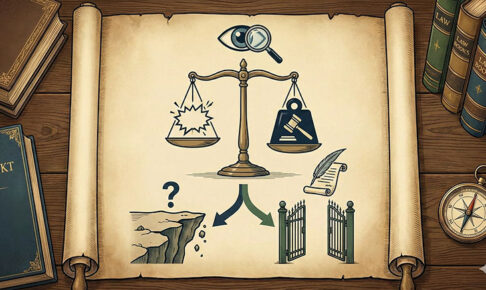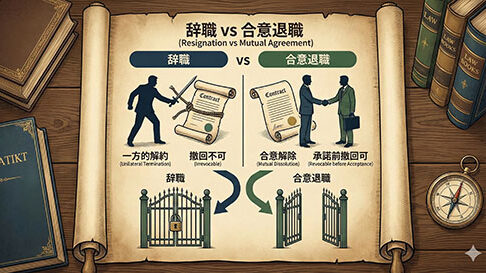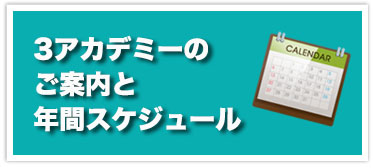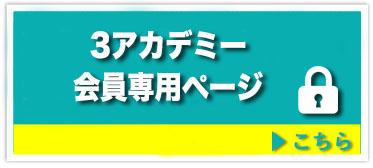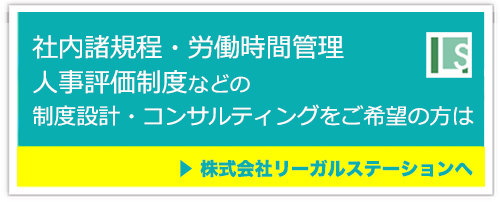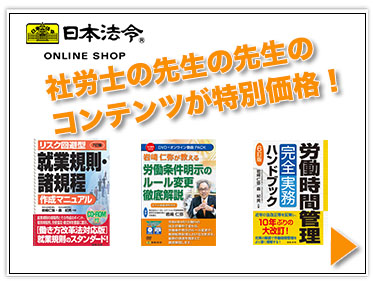こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!
36協定シリーズの第3回は、協定の有効性を根底から左右する「過半数代表者の選出」について解説します。
実は、多くの企業がこの部分で重大なミスを犯しており、せっかく締結した36協定が無効となるケースが後を絶ちません。今回は判例も交えながら、正しい選出方法と形骸化という構造的問題について深く掘り下げていきます。
過半数代表者とは?
労働組合が組織されていない事業場において36協定を締結する場合、その当事者となるのは「労働者の過半数を代表する者」(過半数代表者)です。この過半数代表者の選出方法の適正性は、協定の有効性を根底から左右する極めて重要な要素です。
トーコロ事件が示した厳格な基準
この点に関するリーディングケースが、トーコロ事件(最判平13.6.22)です。
この事件では、役員も含む全従業員で構成される親睦団体の代表者が自動的に過半数代表者として36協定を締結していました。
最高裁判所は、このような選出方法では適法な過半数代表者とは認められないとして、協定の効力を否定しました。
判決は、過半数代表者が適法に選出されたというためには、以下の3つの要件を満たす必要があるという厳格な基準を示しました。
1.36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で
2.投票、挙手等の方法による民主的な手続きによって
3.労働者の過半数の支持を得て選出される
また、選出される者は管理監督者であってはならず、使用者の意向によって指名された者であってもならないことが、労働基準法施行規則第6条の2及び判例法理によって確立されています。
形骸化という深刻な問題
しかし、この明確な法的要件にもかかわらず、過半数代表者制度は長年にわたり「形骸化」という深刻な問題を抱えてきました。
特に近年、電子申請の普及や行政手続きの押印廃止という効率化の流れが、皮肉にもこの形骸化を助長している側面があります。
労働新聞が報じるように、電子申請の利便性から労使間の合意形成という本質的なプロセスが軽視され、協定書を兼ねる届出書に労働者代表の署名・押印がない「協定書なし」の状態のまま届出が行われる事例が増加し、労働基準監督署が指導を強化する事態となっています。
形骸化の実態と法的リスク
形骸化の実態は深刻です。使用者による一方的な代表者の指名や、協定内容を十分に理解していない技能実習生を代表者として選任するといった悪質な事例も後を絶ちません。
こうした不適切な選出によって締結された36協定は当然に無効であり、それに基づいて行われた時間外労働はすべて違法となります。結果として、企業は多額の未払い割増賃金の支払いを命じられたり、書類送検されたりする法的リスクを負うことになります。
形骸化の構造的要因
この形骸化の背景には、単なる使用者のコンプライアンス意識の欠如だけでなく、構造的な問題が存在します。
労働組合のない職場で選ばれる過半数代表者は、多くの場合、本業を抱える一従業員であり、以下のような困難に直面します。
1.仕事の受動性:人事部門からの依頼を受けて受動的に対応することが多い
2.専門性の欠如:労働法に関する専門知識が不足している
3.使用者への忖度・信頼:使用者との力関係や日頃の信頼関係から、提示された案に強く反対しにくい
これでは、労働者全体の意見を集約し、使用者と対等な立場で交渉するという、制度が本来期待する役割を果たすことは極めて難しいのです。
36協定の周知義務も重要
さらに、締結された36協定が事業場の労働者全体を規律する法規範としての効力を持つためには、その内容が労働者に「周知」されている必要があります。
フジ興産事件(最判平15.10.10)は就業規則に関する判決ですが、この法理は36協定にも類推適用されると解されています。
労働基準法第106条は、周知の方法として、事業場の見やすい場所への掲示・備え付け、書面の交付、電子データによる共有などを定めています。
周知という行為は、二者間の合意を、職場全体のルールへと転換させるための決定的に重要なプロセスです。法的な紛争において、労働者は「見たこともない協定の内容には拘束されない」と主張することが可能であり、その主張が認められれば、当該協定に基づく時間外労働命令は無効と判断されるリスクがあります。
実効性ある制度運用のために
形骸化を防ぎ、実効性ある過半数代表制度を運用するためには、以下の点に注意が必要です。
1.選出プロセスの実質化:単に投票や挙手といった形式を整えるだけでなく、労働者が36協定の内容やその重要性を理解した上で、自らの意思で代表者を選出できるような情報提供と環境整備を行う
2.代表者の権限・保護の強化:代表者が使用者と対等な立場で交渉できるよう、交渉に必要な情報へのアクセス権、交渉や意見集約活動に従事する時間の労働時間としての認定、代表者としての活動を理由とした不利益取扱いからの保護
3.労働者側の意識改革:労働者自身も、過半数代表制度を自らの労働条件を左右する重要な権利かつ責務として捉え、代表者の選出や協定内容の議論に積極的に関与していく姿勢
まとめ
過半数代表者の適正な選出は、36協定の有効性を左右する決定的に重要な要素です。
トーコロ事件が示した3つの要件(目的の明示、民主的手続き、過半数の支持)を満たさない選出は無効であり、それに基づく時間外労働はすべて違法となります。
形骸化という構造的問題を克服するためには、単に形式を整えるだけでなく、実質的な労使コミュニケーションの基盤を強化することが不可欠です。締結後の周知義務も含め、36協定は労使の真摯な対話の上に成り立つものであることを忘れてはなりません。
次回は、電子化・押印廃止がもたらす新たな実務上の注意点について、詳しく解説します。お楽しみに!
「3アカデミー」オンラインサロンでは、さらに踏み込んだノウハウも共有していますので、ぜひご参加ください!
↓↓↓
https://academy.3aca.jp/2024a/