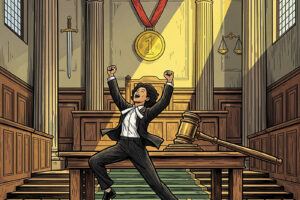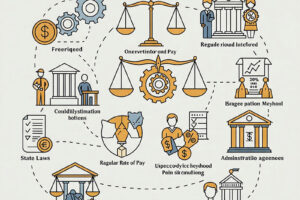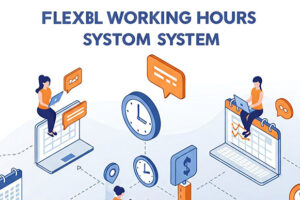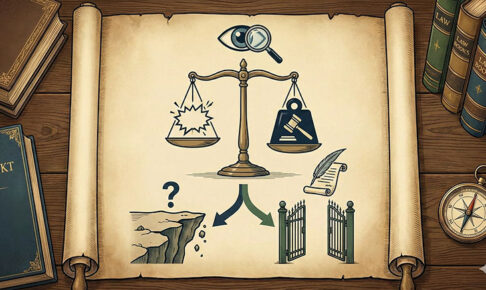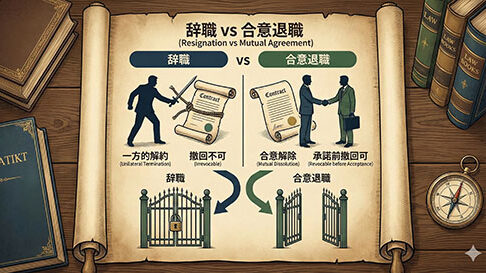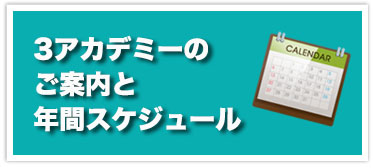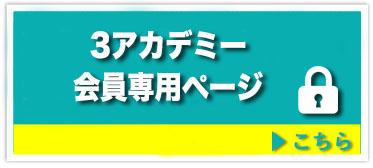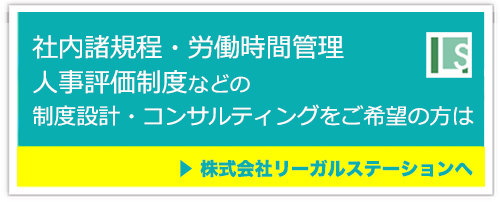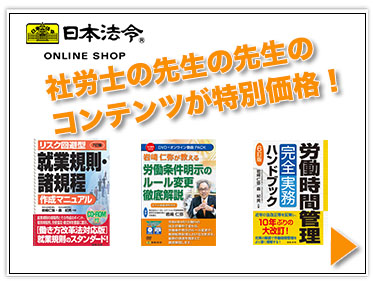こんにちは、分かりやすさNo.1社労士の先生の先生、岩崎です!
前回は欠勤期間から休職への移行プロセスについてお話ししました。
今回は、復職後に残念ながら再び休職が必要となるケースへの対応として、「クーリング期間」の概念と休職期間の通算について、最新の統計データと判例を交えながら詳しく解説していきます。
クーリング期間とは何か?
「クーリング期間」とは、一般的に、私傷病休職から復職した従業員が、一定期間継続して就労した場合に、その後の再休職の取り扱いにおいて、以前の休職期間とは切り離して新たな休職として扱われるための「リセット期間」を指します。
つまり、このクーリング期間を無事に満了すれば、仮に再度同一または類似の疾病で休職するに至っても、新たな休職期間が付与される可能性があるということです。
法的にクーリング期間の長さや設定が義務付けられているわけではなく、その有無や具体的な期間は、各企業の就業規則によって定められます。
企業はどの程度のクーリング期間を設定しているか
労務行政研究所が2024年に実施した調査結果を詳しく見てみましょう。
再休職時に休職期間を通算すると定めている企業において、その通算の対象となる「一定期間(復職後の就労期間)」として最も多かったのは「6か月」で、全体の36.6%を占めています。
次いで「3か月」が18.5%、「12か月」が17.6%となっており、多くの企業が3か月から12か月の範囲でクーリング期間を設定していることが分かります。
神奈川県産業労働支援センターが実施した調査(2013年のデータ)でも、通算規定がある企業において「一定期間」として最も多いのは「6か月」で23.2%でした。この数字は、時代を超えて6か月程度が適切なクーリング期間として認識されていることを示しています。
なぜクーリング期間を設けるのか?
クーリング期間を設ける目的は、従業員の安定した就労状態を確認し、安易な休職の繰り返しを防ぐことで、企業運営の安定性を確保しつつ、従業員にも回復状態を見極める機会を与える点にあります。
特にメンタルヘルス不調の場合、復職後の再発率は大きな懸念事項です。ある調査では、企業の32.4%が「復職者の半分以上が精神疾患を再発した」と回答している一方で、47.1%の企業が「復職者の精神疾患の再発はほとんどない」と回答しており、企業や対象者によって状況が大きく異なることが示されています。
休職期間の通算規定の実情
復職後に同一または類似の疾病が再発した場合の対応として、多くの企業が就業規則に「休職期間の通算規定」を設けています。
この「休職期間の通算規定」とは、復職後、一定期間内(クーリング期間内)に同一または類似の疾病により再度休職する場合、前回の休職期間と今回の休職期間を合算して、就業規則に定める休職期間の上限を管理するものです。
労務行政研究所の2024年調査によると、実に81.3%という高い割合の企業が、復職後「一定期間内」に同一傷病で再休職した場合、休職期間を通算すると回答しています。
これは、多くの企業がこの問題に対して組織的に対応していることを示しています。
神奈川県産業労働支援センターの調査(2013年のデータ)では、同一疾病で再休職した場合の対応について、より詳細な内訳が示されています。
・「復帰後の出勤期間が一定期間内であれば通算される」:33.1%
・「ケースバイケース」:28.4%
・「通算されない」:17.6%
・「復帰後の出勤期間にかかわらず同一疾病ならすべて通算」:17.4%
通算規定があると回答した企業は合計で50.5%となっています。
「同一・類似疾病」の判断の難しさ
休職期間の通算規定を適用する際に課題となるのが、何をもって「同一」または「類似」の疾病とするかの判断です。
特に精神疾患の場合、診断名が変動することもあるため、「類似の事由」という文言を含めることが実務上重要となります。
企業としては、主治医や産業医の意見を参考に、慎重に判断する必要があります。診断名だけでなく、症状や原因などを総合的に考慮することが求められるでしょう。
通算規定の合理性を認めた重要な判例
野村総合研究所事件(東京地判平20.12.19)は、クーリング期間を伴う休職期間通算制度の有効性を支持する上で重要な意味を持つ判例です。
この事件では、メンタルヘルス不調による欠勤の増加と再発の多さを背景に、企業が就業規則を改定し、復職後6か月以内に同一事由で再休職した場合に休職期間を通算する規定を設けたことの合理性が認められました。
裁判所は、特にメンタルヘルス不調のように再発率が高い傷病について、企業が休職の繰り返しに対応する必要性を認め、休職期間の通算規定の合理性を肯定しました。
通算規定がない場合のリスク
就業規則に通算規定がない場合、再度の休職は新たな休職として扱われ、休職可能期間がリセットされる可能性があります。これは、休職が長期化したり、繰り返されたりするリスクを高めることになります。
また、企業の予測可能性や労務管理の観点からも、明確な基準がないことは望ましくありません。
精神疾患と一般疾病の扱い
興味深いことに、労務行政研究所の2024年調査では、95.9%の企業が、精神疾患の場合も一般疾病と同じ休職期間を設定していることが分かりました。
これは、精神疾患特有のクーリング期間や通算ルールではなく、一般的な休職制度の枠組みの中で対応されていることが多いことを示しています。
ただし、精神疾患の特性(再発しやすい、回復に時間がかかる場合があるなど)を考慮した、より柔軟な制度設計を検討する企業も増えています。
制度運用における注意点
通算規定を適用する際は、単に再発の可能性があるという理由だけで、治癒している従業員を退職させることはできません。一般的に、裁判所は、通算規定の適用にあたって、従業員の回復努力、企業の支援状況、疾病の性質などを総合的に考慮し、その公平性を判断します。
また、三洋電機ほか1社事件(大阪地判平30.5.24)では、複数回(4回目)の休職を繰り返した従業員に対し、企業がさらなる休職を認めずに解雇した事案で、解雇が合理的理由を欠くとはいえず、社会通念上相当であると判断されました。これは、企業の休職許容にも限界があることを示唆しています。
まとめ
クーリング期間や休職期間の通算規定は、企業にとってリスク管理の手段であると同時に、従業員にとっても一定の予見可能性を与える制度として機能しています。
統計データが示すように、多くの企業で6か月程度のクーリング期間を設定し、80%を超える企業が何らかの形で通算規定を設けています。企業は、就業規則において「同一または類似の疾病」の定義を明確にし、公平かつ一貫した運用を心がける必要があります。
特に、診断名が変わりやすい精神疾患の場合には、その判断に医学的知見を取り入れることが不可欠です。このような規定がない場合、休職制度の運用に混乱が生じたり、不公平な取り扱いが生じたりするリスクがあります。
次回は、円滑な職場復帰を支援するための「リハビリ出勤制度」について詳しく解説します。制度の導入状況や運用上の留意点、法的な考慮事項などをお伝えしていきます。
「3アカデミー」オンラインサロンでは、さらに踏み込んだノウハウも共有していますので、ぜひご参加ください!
↓↓↓
https://academy.3aca.jp/2024a/